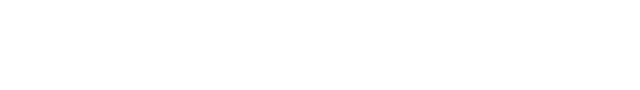脂肪性肝疾患 Steatotic liver disease: SLD
ALDとNAFLD
脂肪肝(Fatty liver)とは肝臓に脂質が過剰に蓄積している状態です。一般的には肥満、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病と関連して指摘される場合があり、大量の飲酒が原因のアルコール性脂肪性肝炎(ALD; Alcoholic liver disease)がよく知られています。しかしアルコール摂取とは関連がなく、非アルコール性の脂肪肝から脂肪性肝炎や肝硬変に進行した状態までを含む一連の肝臓病である非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD; Non-alcoholic fatty liver disease)の注目が高まっています。非アルコール性とは言っても少量のアルコールを飲まれる方(純エタノールとして1日30g未満=ビール750mL、日本酒1合半、ワイングラス2杯半、ウイスキーでダブル1杯半未満)にみられる脂肪肝もNAFLDに含まれます。
NAFLDとNASH
NAFLDの多くは無症状で、病気が進行することも少ないといわれていますが、一部で徐々に悪化して肝硬変や肝臓癌に進行する場合があります。このような状態を非アルコール性脂肪肝炎(NASH; Non-alcoholic steato-hepatitis)と呼びます。NAFLDは超音波検査やCT検査などで脂肪肝があり、他に肝臓の病気がなければ診断されます。一方、NASHは肝臓の組織を調べないと確実に診断することができませんが、血液検査で体内の貯蔵鉄の量を反映するフェリチン値、炎症を評価するCRP値、肝臓の線維化マーカーなどが高値を示すことが多く、診断の参考にはなります。メタボリック症候群があるとNAFLDやNASHを発症しやすく、特に肥満、高血糖、脂質異常は危険因子といわれています。
NAFLDの治療の原則は生活習慣の改善で、食事療法や運動療法を行うことにより、背景にある肥満、糖尿病、脂質異常症、高血圧を改善させることです。NAFLDでは心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患での死亡率が高くなるために、メタボリック症候群の是正と肝障害の進行を抑えることに注意する必要があります。
<日本消化器病学会ガイドラインより一部引用>
新たな概念であるSLD
SLD(Steatotic liver disease)はさまざまな病因による脂肪性肝疾患を包含する疾患概念として新たに提唱され5つのカテゴリーに分類しています。
(1)代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(Metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease; MASLD)
5つの心代謝系危険因子(①BMIまたは腹囲 ②血糖またはHbA1c ③血圧 ④中性脂肪 ⑤HDLコレステロール)のうち少なくとも1つの因子の異常を満たす脂肪肝で、従来の除外診断によらない代謝性因子との関連明確にしています。飲酒量についてはNAFLDと同量(エタノール換算で女性140g/週未満・男性210g/週未満)としています。
(2)代謝機能障害アルコール関連肝疾患(MASLD and increased alcohol intake; MetALD)
中間飲酒者(エタノール換算で女性140~350g/週・男性210~420g/週)の脂肪肝
(3)アルコール関連肝疾患(Alcohol-associated liver disease; ALD)
MetALD以上の飲酒量による脂肪肝
(4)特定成因脂肪性肝疾患(Specific aetiology SLD)
①薬剤誘発性 ②Monogenic disease(ウィルソン病など)③Miscellaneous(低栄養、HCV感染など)
(5)成因不明脂肪性肝疾患(Cryptogenic SLD)
*NAFLD, NASHの病名変更について(日本肝臓学会 2023.9.29)
*脂肪性肝疾患の日本語病名に関して(日本消化器病学会 2024.8.22)